| ヘブライの館2|総合案内所|休憩室 |
No.b1fha505
作成 1998.5
●『ヒトラーのテーブル・トーク』(三交社)という本があるが、この本は1941年から1944年にかけて、ヒトラーが側近に語りかけた会話を速記録してまとめ上げたものである。
当時、ヒトラーから最も信頼されていた秘書のマルチン・ボルマンが速記録を訂正、また本人から承認を取り、かつ個人保管していた資料なので、俗に『ボルマン覚書』とも呼ばれている。


(左)ヒトラーに忠実な側近中の
側近だったマルチン・ボルマン大将
(右)『ヒトラーのテーブル・トーク』
ボルマンはドイツ敗戦直前まで、総統秘書長、
副総統、ナチ党官房長として絶大な権力をふるった。
ヒトラーの卓上談義を記録した『テーブル・トーク』は、
「公式記録」として残されたものであり、俗に
『ボルマン覚書』とも呼ばれている。
●この本の「解説序論」で、イギリスの高名な歴史家ヒュー・トレヴァー=ローパーは次のように書いている。

オックスフォード大学の歴史家
ヒュー・トレヴァー=ローパー
「1939年にヘルマン・ラウシュニングの発表した、1932~34年という権力掌握の微妙な時期にあったヒトラーのテーブル・トークの記録『ヒトラーとの対話』(邦題『永遠なるヒトラー』)は世界中を驚かせた。しかし1939年当時でさえ、ヒトラーの残酷さ、彼の途方もない野望を受容することができなかった世界はその記録をまゆつばものだと考えた。現在では一応受け入れられているようであるが、なお疑念をお持ちの読者はぜひ一度ご自分でお読みいただきたい。〈中略〉
東プロイセンの地主貴族階級出身で保守派であったラウシュニングは、小耳にはさんだヒトラーの『千年王国思想』に戦慄を覚え、遂に1934年、彼はこの怪物のもとを去り国外へ逃亡した。そのため西側世界に向かってわずかに開かれていたヒトラーの思想への覗き窓は、1934年を境に突如閉じられてしまう。
いずれにせよ1939年に出版されたこの覗き窓を覗き込んだ人、そこで垣間見たものを信じた人は非常に少なかった。そしてその後の10年間、ナチス総統本部におけるおしゃべりはすっぽりと秘密のべールに包まれることになる。もっともそれ以前も本来は秘密だったのであるが。
本書(『ヒトラーのテーブル・トーク』)は、そのラウシュニングの記録のちょうど10年後の時期、すなわち1941年から44年にかけてのヒトラーの卓上談義(テーブル・トーク)の記録である。しかもある種の偶然に近いラウシュニングの記録とは異なり、こちらは公式記録として残されたものである。」
※ 注意:ここで語られているラウシュニングの記録内容については、当館作成のファイル「ヒトラーの超人思想の謎」をご覧下さい。


(左)ヘルマン・ラウシュニング(元ナチ党員)
(右)彼が発表した『ヒトラーとの対話』
(邦題『永遠なるヒトラー』)
●さらにトレヴァー=ローパーは次のように書いている。
「本書収録の談話は、ヒトラーの思想を反映する粗野さ、独断主義、ヒステリー、些事への執着などに満ち満ちている。読者には嫌悪感ばかりが先立つ内容かもしれない。しかしそこには紛れもないヒトラーの思想の核が見えている。
これはヒトラーの天才を映し出す鏡だといえよう。そしてこの談話こそが、かの忌まわしい天才を解放することができるもの、解放するために不可欠なものであると私は信じるのである。」
「ヒトラーは自らを現代のメシア(救世主)だと考えていた。そのような宗教的称号で呼ばれることに言葉の上では異を唱えてはいたが、現代の危機を理解しこれを救うことができるのは自分しかないと信じていたのは明らかである。
彼にとって、第一次世界大戦でのドイツの敗北はドイツにとっての危機であるばかりではなく、人類文明そのものの危機でもあった。この危機は、時代を見通す目で歴史を学んだ者、また時代の交替という歴史の大変動期をコントロールしうる能力を備えた者のみが理解できる、人類史上でもまれな危機なのであった。
我々は彼の思想を理解しようと思うのならば、彼の思想の核をなしていたこの『終末的歴史観』を理解しなければならない。彼はこの歴史観の枠内で自らの使命を自覚し、またこの歴史観をバックに人を判断したからである。
ヒトラーがこの歴史観を明言したのは勝利の美酒に酔っていた1941年のことではない。獄中で敗北の苦杯をなめていたかに見える1923年だったのである。」

アドルフ・ヒトラー
●このトレヴァー=ローパーが語るように、『ヒトラーのテーブル・トーク』にはヒトラーの思想の核が見えている。
この本の中でヒトラーは自らの宗教観・宇宙観を率直に語っているが、そこには「神」への篤い信仰心とともに、キリスト教や共産主義やユダヤ人への憎悪が混じっているのが特徴である。
※ ヒトラーは「ロシア革命」を「ユダヤ・ボルシェヴィキ」による革命だとみなしていた。

無神論的共産主義を唱えた
ユダヤ人カール・マルクス
●ところで、一般にヒトラーは「反キリスト」の男として語られる場合がある。ヒトラーのキリスト教嫌いは有名だからだ。しかしヒトラーは「キリスト教」を嫌ってはいたが、「イエス・キリスト」という男を嫌ってはいなかった。むしろ敬意を払ってさえいた。
興味深いことに、ヒトラーはイエス・キリストはユダヤ人ではなく「アーリア人」だと信じていたのである。そしてイエス・キリストの直接的な教え(教義)はユダヤ人によって著しく歪められたと信じていたのである。
つまり、ヒトラーはイエス・キリスト本人を憎んでいたのではなく、彼の死後に形成された「キリスト教」という名を掲げた「宗教サークル(組織)」を憎悪していたのだ。
●ヒトラーは使徒パウロ以降のキリスト教を「ユダヤ教の一派」として激しく論難しながら、
一貫して自らをイエス・キリストに擬し、「ユダヤ人の追放にあたり、私は神殿を粛清したイエス・キリストを思い出す」とまで言っていたのである。

フランスの画家ヴァランタン・ド・ブーローニュが描いた
「神殿から商人を追い出すイエス・キリスト」(1618年作)
常に冷静で温厚なイエスがキレて大暴れするという衝撃的な話が『新約聖書』
には載っている。それによると、イエスは祈る者のためにあるエルサレムの神殿で
生贄用の動物の売買や両替をして「金儲け」をしていた悪徳商人たちを目撃して激怒。
落ちていたロープを結んでムチを作り、振り回しながら動物たちを追い散らし、両替屋
の台を蹴り倒して金を飛び散らかしたという。「こんなものはここから出せ! 私の
父の家を商売の家にしてはならぬ!」とイエスに怒鳴られたユダヤ商人たちは、
イエスの激しい暴力行為に文句を言うことができず、神殿を後にしたという。
(この大騒動はイエスの「宮清め」とか「神殿粛清」と呼ばれている)。
●さてここからは、『ヒトラーのテーブル・トーク』の中で、ヒトラーの「宗教観・宇宙観」が色濃く出ている部分(談話)を参考までにピックアップしておきたい。
以下は全てヒトラーが語った言葉である↓



──────────────────────────────
◆「ユダヤ人は宗教の名の下に、それまで寛容が支配していた世界に非寛容を持ち込んだ。ローマ人の宗教は限界を知る人間の謙遜さの表れだった。知られざる神々への神殿までつくるほどだったではないか。
かつてユダヤ人は古代社会にキリスト教を持ち込み、破滅をもたらした。今、また社会問題の解決とやらを口実に同じことを繰り返そうとしている。同じ手口だ。かつてサウロが使徒パウロに変身したように、現代、モルデカイがカール・マルクスになったのだ。」
◆「本来キリスト教は破壊的なボルシェヴィズムの顕在化にすぎなかった。だが後にキリストと呼ばれたガリラヤ人は、全く違うものを目指していたのである。彼はユダヤ人に対抗する民衆のリーダーと見なされていたにちがいない。ガリラヤはローマがおそらくゴール人の軍団を駐留させていた植民地であり、イエスがユダヤ人でなかったのは確かである。ユダヤ人はといえば、イエスのことを娼婦の子、娼婦とローマ人の子供と見なしていた。
イエスの教義を決定的に歪曲したのは聖パウロである。彼は個人的野心を秘め、巧みにやってのけた。
ガリラヤ人(イエス・キリスト)の目的は祖国をユダヤ人の圧政から解放することであった。イエスはユダヤの資本主義・物質主義に対抗し、そのためユダヤ人に抹殺されたのである。」
◆「ローマ人ほど寛容な人々はいなかった。誰でも自分の神を拝むことができ、神殿にはまだ知られざる神のための場所が空けてあった。しかも誰でも自分の好きなように祈り、自分の好みを公言する権利もあったのである。
聖パウロはローマ国家に対する戦いを遂行するのに、こういった状況をうまく利用するすべを心得ていた。何も変化させず、従来の方法もそのまま踏襲した。宗教上の指示のように見せかけて、僧侶たちは国家に反するように信者をそそのかすのである。
ローマ人の宗教的考え方はすべてのアーリア民族に共通するものがある。一方、ユダヤ人は昔も今も黄金の子牛だけを拝み続けているのである。ユダヤの宗教には形而上学的なものも基盤もない。あるのは忌まわしい物質主義だけである。来世の具体的なイメージにもそれは現われている。ユダヤ人にとっては来世はアブラハムの懐と同じなのである。
ユダヤ人が宗教的なコミュニティという性格を見せ始めるのは聖パウロの時代からである。それ以前は単なる人種的コミュニティにすぎなかった。聖パウロは宣伝手段として宗教を利用した最初の人間である。ユダヤ人がローマ帝国の崩壊を導いたとするなら、それはユダヤ人に対立するアーリア人の地域的な運動を超世俗的宗教に変えた聖パウロのせいであろう。その宗教は人間の平等と唯一神への服従を求めていた。これがローマ帝国の死を招いたのである。」
◆「聖パウロの努力にもかかわらず、キリスト教の教えがアテネでは普及しなかったのはおもしろい。この貧乏ったらしいバカな考えに比べて、ギリシアの哲学ははるかに程度が高く、使徒の伝道を聴いたアテネ市民は大笑いしたという。しかしローマでは聖パウロを受け入れる下地が整っていた。人類は平等という考えが、生活の基盤を持たない大衆の心をつかんだのである。
だがローマの奴隷の実像は、我々が想像するものとはかけ離れている。実際のところ、奴隷とは戦争の捕虜(今日の意味で)で、解放される者も多く、ローマ市民になる可能性もあった。この奴隷に、今日のイメージのように身分が低いという考えを植えつけたのが聖パウロである。
ローマでは、ゲルマン民族は深い尊敬を勝ち得ていた。ゲルマンの血はたえずローマ社会に新しい命を吹き込んでいた。一方、ユダヤ人はローマでは軽蔑されていた。ローマ社会はこの新しい教義に反感を抱いたが、純粋な段階のキリスト教は民衆を動かして反乱を起こさせた。ローマはボルシェヴィキ化され、ボルシェヴィズムが後のロシアと同じ結果をローマにもたらしたのである。
後になってゲルマン精神の影響で、キリスト教はそのあからさまなボルシェヴィキ的性格を徐々に失っていった。いくらか我慢できるものになったのである。今日では、キリスト教がよろめくと、ユダヤ人がボルシェヴィキ的な形のキリスト教を再び持ち上げるのである。ユダヤ人はこの実験をもう一度繰り返すことができると思っている。昔と同様今日の目的も、人種的統一を乱して国家を滅ぼそうというのである。ロシアでユダヤ人が組織的に何十万もの男を移住させたのは偶然ではない。強制的に置き去りにされた女性は他の地域から来た男たちに回される。人種の混交を大規模にやっているのである。
昔も今も、目的は美術と文明の破壊であった。ボルシェヴィキが力を持った時、ローマで、ギリシアで、どこででも、破壊しないものがあっただろうか? ドイツでもロシアでも同じことをしてきたのである。比べてみたまえ、片やローマの文明と美術、神殿や邸宅、片やカタコンベのお粗末なやっつけ仕事。昔は図書館も破壊された。ロシアでもそうだっただろう? おかげで恐ろしくレベルが落ちてしまった。
中世になると、破壊のシステムは殉教や拷問という形をとるようになった。昔はキリスト教の名のもとに行われ、今はボルシェヴィズムの名のもとで行われている。昨日の扇動者はサウロだった。今日の扇動者はモルデカイである。サウロは聖パウロとなった。モルデカイはカール・マルクスである。このような害虫を駆逐することは、人類に対するこの上ない貢献である。」
◆「イエス・キリストはアーリア人だった。パウロがイエスの教えを利用して犯罪者どもを動員し、『原始共産主義』を組織したのだ。この時、それまでの天才、ギリシア・ローマ人の時代が終わったのだ。
人間たちが自分の前にひれ伏すのをみて喜ぶ『神』とはいったい何者なんだ。その神は自分で罪を犯しやすい状況をつくり、悪魔の助けを借りて人間に罪を犯させるのに成功、それから処女に男の子を生ませ、その男の死で人間の罪をあがなった。何ともばかばかしい話だとは思わんのか!
マホメットの説く天国に夢中になる人間の気持ちは私にも理解できる。また、自然の驚異を畏敬する人間の気持ちも分かる。だが、キリスト教の無味乾燥な天国だけは分からん。生きている間はワーグナーのすばらしい音楽に聞き惚れていた君らが、死後、シュロの枝を振りながらハレルヤを歌うしかない世界、赤ん坊と老人しかいない世界に行くのだぞ。
キリスト教! これは腐った脳味噌の産物だ。これ以上に無意味でひどいやり方で神を馬鹿にした宗教はない。パンと葡萄酒がキリストの体と血だなどと真面目に信じている人間よりは、タブーを信じている黒人の方がはるかに上等だ。」
◆「天の摂理は、与えられた頭脳の使い方を知っている人間に勝利をもたらす。法律家たちによってつくり出された法概念と自然の法とはほとんど一致するところがない。しかし、民族の古い知恵の中には自然の法そのものともいうべきものが見出される。いわく『天は自らを助くる者を助く』。人間が摂理を忘れてしまっているのは明らかだ。
一般に天地創造と呼ばれている出来事は紛れもない事実だ。それをさまざまに解釈しているのは、人間の側の勝手なのだ。神はなぜ、すべての人間に真理を理解する能力を与え給わなかったのだろうか。
現在、世界人口のたった十分の一しかカトリック教徒でないということは周知の事実だ。また、さまざまな宗教が共存しており、信じる者にとってはそれらすべてが真実であるのも明らかだ。さらに、キリスト教が受け入れられているのは人類の歴史のほんのわずかの期間にしかすぎない、ということもいわずもがなだ。
神は神の姿に似せて人間を創造し給うた。ところが、原罪とやらのおかげで、我々は額に汗してパンを得る、現実の世界の姿に似た人間なのだ。
50万年の間、神は自分がつくった世界をただじっと眺め明かしていた。そしてある日突然、地上に一人息子を送る決心をする。その後の複雑怪奇なストーリーは諸君のご存知のとおりだ。」
◆「信仰とは、信じない者には力によって強制すべきものであるらしい。もし人間が神を信じることを神自身が望んでおられるのであれば、なぜ、責め苦によってその目的を果たそうとなさるのだろう。
ついでながら一つ言っておきたいことがある。よきカトリック教徒だと自認する人々の中でも、教会の宣伝するたわごとを全面的に信じている人はほんのわずかしかいないということだ。熱心に教会に行くのは、もう人生から降りて諦念している婆さんたちだけだ。教会の広めるたわごとは、すべて無用の長物だ。そんなものにかかずらって時間をむだにしてはいけない。
教会の組織する組合には、物質的ご利益のみを求めてそれ以上のものには目も向けないという輩が意外に多い。また、しかめっ面こそが信仰だと思っている連中もいる。さらに驚いたことには、神に仕える聖職者どもが実は無神論者だということすらあるのだ。」
◆「自分の主張を通すためには祈りで十分だと信じるのであれば、なぜ血を流して戦うのだ? スペインの坊主どもは『我々は祈りの力で防衛する』といってしかるべきだった。ところが実際には、教会を救うには、異教徒を雇ってでも戦う方が妥当だと考えたではないか。もし私が哀れな罪深い人間のまま悔い改めもせず死んだとしても、ああ、それで結構。それでも死ぬ前に10マルクも献金すれば、私の生前の行いは多少はよく評価してもらえるとでもいうのだろうか。それが神の望むところなのか?
素朴な労働者や田舎娘が教会の謳い文句にのせられるのは理解できる。しかし、どうしても容認できないのは、インテリ層までが迷信宣伝の共犯者となったり、何千何万という人間が迷信と愛の名の下に抹殺されたりしたことなのだ。嘘偽りの上に築かれたものがいつまでも持ちこたえるとはとうてい信じられない。私は真実を信じる。長期的には真実が必ず勝つと確信しているのだ。
宗教に関しては、我々は寛容の時代に入りつつあるのかもしれない。誰もが自分に最もふさわしい形の救いを求めるのが許される時代だ。
古代社会にはこの種の寛容さがあった。改宗の必要などなかったのだ。私が教会堂に入って行ったとしても、それはイエスやマリアの像を打ち倒すためではない。美しいものを求めて行くのだ。」
◆「私は私自身の信念に従って行動している。他人が黙祷するのを妨げるつもりはない。しかし、神への冒涜は許せない。私のために頼んでもいない祈祷などしてくれるな。
天の摂理によって私がこの世に生を受けたというのであれば、私の存在は至高の意志によるものだ。教会などには何の関係もない。教会は魂の救いを売り物にインチキ商売をしている。残酷極まりない。私の考えを力ずくで他人に押しつけることはできない。しかし、他人の肉体や魂に苦痛を与えて喜ぶような人々には、私は恐怖すら覚える。
我々の時代はキリスト教という病気の絶滅の時代だろう。もっとも、完全に絶滅するまではあと100年か200年はかかるかもしれないが。これまでの預言者たち同様、残念ながら私にも約束の地を見はるかすことはできない。
我々は陽光あふれる時代、寛容の時代へと入って行くのだ。そこでは、人は神から与えられた能力を自由に伸ばせるようになるのだ。何よりも重要なのは、より大きな虚偽が、今や絶滅途上にある虚偽に代わって入り込むのを阻止することだ。すなわち、ユダヤ共産主義の撲滅だ。」
◆「キリスト教の到来は人類にとっては最悪の事件だった。
ボルシェヴィズムはキリスト教の私生児である。どちらもユダヤ人の生み出したものだ。宗教に嘘を持ち込んだのはキリスト教である。ボルシェヴィズムも同じような嘘をつく。人間に自由をもたらすといいながら、実際には奴隷にしようとしているのだ。
太古の時代には人と神との関係は本能に根ざしたものだった。それは寛容に彩られた世界だった。敵対するものを愛の名において滅ぼした宗教はキリスト教が最初である。そのキーワードは非寛容なのである。
キリスト教がなければイスラム教もなかっただろう。ローマ帝国はゲルマン民族の影響のもと世界帝国へと発展したことだろう。15世紀にわたる文明を一瞬のうちに失うはめには陥らずにすんだことだろう。キリスト教のおかげで人が精神的生活に目覚めたなどといってほしくはない。それは物事の自然な進展の結果である。ローマ帝国の崩壊は数世紀に及ぶ暗黒をもたらしたのだ。」
◆「リンツ、ペストリンクベルクの山に建てる天文台のイメージがありありと目に浮かぶ。異教徒どもの教会を潰し、その跡に建った古典的なたたずまいの建物。日曜ごとに何千何万という巡礼が訪れ、宇宙の偉大さに触れるだろう。入り口にはこう刻まれている──『天は永遠なるものの栄光を表す』。我々はこうして宗教心、謙虚さを国民に教えるのだ。ただし、坊主ども抜きだ。
人は真理のかけらをつかむことはできる。しかし、自然を支配することはできない。むしろ自然への依存を知らねばならない。この認識は、教会の迷信的教えよりはるかに深い人生の深みへと人を導く。
キリスト教は人類最悪の退行現象だ。悪魔の被造物ユダヤ人は、人類を15世紀も退行させた張本人だ。さらにそれ以上に悪魔的なのがユダヤ共産主義の勝利だ。万が一、共産主義が勝利を収めるようなことになれば、人類は笑いと喜びの能力を失い、灰色の絶望を背負った顔なき群衆と化すだろう。」
◆「古代の宗教の神官は自然により近く、物事の意味を求めるにも謙虚さを持っていた。ところがキリスト教は、その矛盾にみちた教義を力ずくで宣伝、強制する。非寛容と迫害を内包した血まみれの宗教だ。
私の建てる天文台は建物だけで1200万マルクはかかるだろう。プラネタリウムだけでも200万の値打ちがある。プトレマイオス(2世紀、ギリシアの天文学者)の天文台の方が安上がりだ。プトレマイオスの頃、地球は宇宙の中心だった。この考えをひっくり返したのがコペルニクスだ。今日、我々は我々の住む太陽系は多くの中の一つだということを知っている。この宇宙の驚異をできるだけ多くの人に知らしめるのが我々にできる最高の仕事だ。いずれにせよ、我々を300年以前ではなく現在に生かしめてくれた天の配剤に感謝しようではないか。
当時は町の辻々に火刑用の杭が立っていたような時代だ。虚偽と非寛容に対し最初に反抗する勇気を持った人々に、今日の我々は大きな借りがあるのだ。驚くべきは、イエズス会の神父たちがその勇気ある人々の一部だったということだ。」
◆「宇宙は地球にしろ、太陽にしろ、他の惑星にしろ、構成物質は同じである。今日では有機生命体がいるのは地球だけとは考えられない。
科学の知識は人を幸せにするだろうか? それは分からない。人が間違った知識でも幸せになれることは分かっている。人は寛容さを磨く必要があるようだ。前世紀の科学者は、人間は創造物の王者であると主張していたが、馬鹿なことだ。そのくせ、急ごうと思えば低能な哺乳類の馬に頼るしかないというありさまなのだぞ! こんな馬鹿げた主張があるものか。
ロシア人が僧侶たちを攻撃したのは結構なことだ。だが『至高の力』という考え方まで攻撃するべきではなかった。我々はか弱い生き物であり、創造する力が存在することは事実である。それを否定するのは愚の骨頂である。こんな場合には、何も信じないよりは嘘でもいいから信じた方がましである。
創造物の上に立っていると大見得を切ったケチなボルシェヴィキの教授は誰だったかな? あんな輩こそやっつけねばならない。物質主義的思想の持ち主は互いに責め合い、つぶしあうだけだが、教義なり哲学なりを信じる我々には常に可能性が残されているのである。」
すべての物事は周期的に現われるものだ。宗教はいつも自由な探求精神と対立している。教会と科学との対立は、時として火花が散るほど激しくなる。自らの利益を守ろうとする教会が時にはわざと譲歩し、結果として科学が急進性を失うこともある。
科学が独断的な態度をとるようになれば、それは教会と同じになってしまう。神が雷光を起こすという時、ある意味でそれは正しい。しかし教会が主張するように、神が落雷を発生させるわけではない。自然現象についての教会の説明が間違っているのは、教会に下心があるからである。
己の弱さと無知を知る者には真の敬虔さがある。方舟や礼拝堂にしか神を見られないのでは、本当に敬虔とはいえない。それは見せかけにこだわる人間にすぎず、雷が鳴り、稲光が光れば、犯した罪を罰せられるのかと脅えるだけなのだ。」
◆「私はヘルビガー(氷河宇宙進化論を唱えたオーストリア出身のエンジニア)の宇宙理論を信じたい。
我々の時代より一万年前に地球と月が衝突して、月の軌道が今のように変わったというのは決して不可能なことではない。地球が月の大気を引き寄せて、そのために我々の惑星の環境が急激に変化したということもありうる話である。この衝突の前は人間はどの高度でも生活することができたと考えられる。気圧の制約がないという単純な理由からである。大地は口を開き、できたばかりの裂け目に水が流れ込み、爆発が起こり、そして豪雨が降り始めたのではないか。これでは人間は高いところに逃げるしかなかっただろう。
いつの日か、誰かがこうした事実を直感的に関連づけて疑問に答えてくれれば、精密科学がその跡づけをすることができるようになる。それ以外には我々の現在の世界とそれに先立つ世界との間のヴェールを取り除く方法はないだろう。」
◆「今後は有機的世界と非有機的世界の間には境界はないと考えよう。
最近の実験によれば、生命体と非生命体を区別するものは何なのか疑問が生じているようだ。この発見に対して教会はまず反発し、そして自らの『真理』を教え続けるだろう。だが、いつか科学の破城槌が教理を打ち砕く日が来るだろう。当然のことだ。人間精神が神秘のヴェールをはがせば、結論は否応なく出るのである。
顕微鏡を見ると人間は無限に大きなものだけでなく、無限に小さなものにも取り囲まれていることが分かる。マクロコスモスとミクロコスモスである。
こうした視野の大きな考察に、自然観察で得た事象がつけ加えられるのである。例えば断食のような衛生学的実践は人間のためにいいこと、などである。古代エジプトでは医学と宗教に区別がなかったのは決して偶然ではない。
近代科学がこうしたデータを無視するものなら、人類にとって益にはならない。他方、迷信が人類の進歩の足かせになってもいけない。そういったことと、宗教の消滅を当然と見ることも、ともに許されることではない。」
以上、『ヒトラーのテーブル・トーク』(三交社)より
── 当館作成の関連ファイル ──

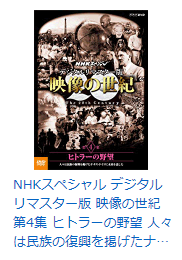
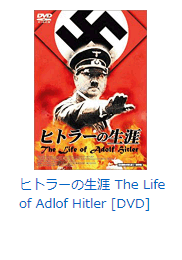

Copyright (C) THE HEXAGON. All Rights Reserved.