| ヘブライの館2|総合案内所|休憩室 |
No.a6fhc106
作成 1998.1
■Part-1
19世紀末、ユダヤ人たちは興奮した。ユダヤ世界帝国の完成が近いと察知したからだ。19世紀までにユダヤ人国際銀行家たちは、事実上、世界諸政府の通貨をほとんどを支配していた。
欧州で50年間「神秘の男」と呼ばれてきたロシア生まれのユダヤ人バジル・ザハロフは、第一次世界大戦を引き起こした人物といわれる。コンスタンチノープルで6歳のときから売春宿の客引きをはじめ、ポン引きの次に強盗殺人を働きアテネに逃げた。アテネで武器商人の会社につとめて「ビジネスマン」になり上がった。元ポン引きの才覚にかかっては、真面目な政府の武器調達担当官らはひとたまりもなく手ごめにされた。そしてザハロフは億万長者になった。
カネで黒い過去を消す努力をしたが、息子と財産相続問題で争ったさいに裁判所で黒い過去が公表され敗訴した。しかし1億ドルの蓄財者ザハロフは実子にビター文も払わなかった。

ロシア生まれのユダヤ人
バジル・ザハロフ
※ 死の商人として暗躍し、一部の
研究家の間では、第一次世界大戦を
引き起こした張本人だとされている
1890年当時、世界最大の軍需会社であったイギリスの「ヴィッカース社」は1897年に2社を買収した。買収された会社の大株主だったザハロフは、「ヴィッカース社」の役員を務めることになる。「ヴィッカース社」はロスチャイルド家の持株会社だった。ロスチャイルド家は政府に融資協力する条件として、貸付金の半分を武器調達費用に当てさせた。購入武器の増加は戦争準備の強化につながる。当時の欧州ユダヤの大半が、そのやり方で非ユダヤ諸国に武器を売りつけ、戦争体制を整えさせた。
その一方で、貧しいユダヤ人が続々とゲットーを出はじめた。年間60万人がイギリスへ100万人がアメリカへと移民した。彼らは移民先政府の要職を占めはじめた。イギリス外務省はなまりの強い外国人省と呼ばれた。移民ユダヤ人の一部は各国政府で閣僚の座を勝ちとった。フランス蔵相はクロッツ、イタリアはルザッチ、ドイツはレンベルグ、イギリスはアイザックス、とユダヤ人は軒並み蔵相と法相の座を占めた。イギリスの有給領事館員350人中200人が外国生まれで、120人はユダヤ人だった。
当時、全欧州の政府は、ユダヤ人が国益に影響する機密や特許を最高値をつける者に売ったために、財政スキャンダルやスパイ・スキャンダルに揺れたものだった。非ユダヤ人マルコーニが無線通信を発明すると、ユダヤのアイザックス家が所有権を有利な条件で入手した。アメリカの支部RCAはロシア系ユダヤ人デービット・サーノフが使用権を握った。

アメリカのテレビ放送の父
デービット・サーノフ
※「RCA」を創立して「NBC」を
最大級のマスコミ企業に育て上げた
1912年、当時のイギリス首相ロイド・ジョージと蔵相ルーファス・アイザックスは、アイザックス兄弟の「マルコーニ社」社長ゴッドフリー・アイザックスとシェル石油を所有するユダヤ一族のイギリス郵便局長サミュエルから10万株を贈られた。この贈収賄事件は発覚したが、ロスチャイルド家が介入して事件は簡単に闇に葬られ、収賄者たちは公職にとどまったばかりか、蔵相アイザックスはロスチャイルド家から爵位までもらった。
ユダヤは首相ロイド・ジョージを買収して自在に操った。ロスチャイルド家と懇意のザハロフは、首相に自分の妻を接近させて不倫問題を仕かけた。また、イギリスに流れこんできたハンガリー系ユダヤ人のトレビッチなる男を側近にして、イギリス国教会の牧師兼議員に仕立ててスパイを働かせた。
第一次世界大戦は、ザハロフらユダヤ一族の武器商人らが入念に仕組んだとおりに勃発した。借金と引き換えに武器を背負いこまれた各国政府は、あり余るほどの武器・弾薬を消費した。非ユダヤ人の殺戮が進むなか、ザハロフは莫大な財産を残した。
イスラエルの初代大統領になるロシア生まれの化学者でシオニズム運動の指導者ハイム・ワイツマンは、第一次世界大戦中に致命的効果を発揮する毒ガスを発明した。ワイツマンはこの毒ガスを、イギリスとの交渉の武器にした。パレスチナ入手のためのシオニズム運動をイギリスが支持すれば、イギリスにも毒ガスを使わせるという取り引きだった。イギリスは同意してバルフォア卿がロスチャイルド卿にあてた1917年11月2日付けの手紙で正式に合意した。

ハイム・ワイツマン
※「世界シオニスト機構」の総裁を務め、その後、
何年にもわたって世界のシオニズム運動の
指導者となった。イスラエル建国後、
初代イスラエル大統領になる。

フランス・ロスチャイルド家の
エドモンド・ロスチャイルド
※ 彼は19世紀末からパレスチナへ入植するユダヤ人たちに、
「匿名の寄贈者」というサインの付いた「小切手」を送り続け、
彼らを全面的にバックアップしていた。そのため
「イスラエル建国の父」と呼ばれている。


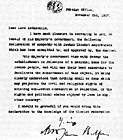
ロンドン・ロスチャイルド家のライオネル・ロスチャイルド(左)と
イギリス外相アーサー・バルフォア。右の画像はバルフォアが
ライオネル・ロスチャイルド宛に出した手紙=
「バルフォア宣言」(1917年)
ところが、「アラビアのロレンス」の名で知られるT・E・ロレンスはアラブ人を説得してトルコに反旗を翻させ、イギリスを支持するよう工作した。その見返りにイギリスは、ユダヤ人をパレスチナから締め出すことを約束していた。
にもかかわらず、バルフォア卿はロスチャイルド卿とのあいだで毒ガス使用を交換条件にユダヤ人のパレスチナ「帰国」を約束してしまったのだった。ロレンスは、アラブに対するイギリスの約束反故に嫌気がさして、公的生活から身を引いた。イギリスの裏切りは、世界の強国大英帝国の斜陽化につながり、イギリスは二流国になり下がった。
ロレンスの死が暗殺だったことを、チャーチルはイギリス秘密情報機関から知らされる。知らせた情報員の背後にユダヤがいた。ロレンスの死は見せしめだとチャーチルに知らせるためだ。ユダヤがこのようにわざとリークした理由は、チャーチルにユダヤ蔑視をやめさせること、政府財政破綻を救う融資をユダヤから受けさせることにあった。それらを実行しなければ、ロレンスと同じ姿となるぞという脅しである。


(左)イギリスの情報将校だったT・E・ロレンス中佐
(右)イギリスの大作映画『アラビアのロレンス』
(1962年制作/ピーター・オトゥール主演)

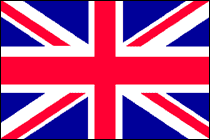
イギリスのウィンストン・チャーチル首相
チャーチルははねつけたが、政府財政の悪化はくい止めねばならない。チャーチルはアメリカのユダヤ国際資本家を訪れる。ウォール街を見学したのち、訪問先のユダヤ資本家のアパート付近で突然自動車事故に遭う。九死に一生をえて助かったものの、ニューヨークで短くはない入院生活を余儀なくされる。イギリスに戻ったチャーチルは、「事故」はユダヤの指示にしたがった警告つまり脅迫行為だったことを知る。観念したチャーチルは、抵当権をユダヤにあずけて融資を受ける。そのさいにユダヤ資本家らは当然のようにイギリスに戦時体制をとらせ、ヒトラーとの政治対決をし向けた。チャーチルはそれまで「ヨーロッパのジョージ・ワシントン」と絶賛してきたヒトラーを、そのときから「ファシスト」呼ばわりするようになる。
一国の首相が突然その要職を辞したり、首をはねられたり、宗旨変更して国民を仰天させたりすることは、このように現実にある。その背後にはかならず因果関係(人間の意志)が存在している。
■Part-2
ベラスコは、現在もなおいわば歴史の裏街道を悠々と歩き、遠慮のない発言を繰り返している。そのたびに周囲はハラハラさせられている。
1932年に世界の檜舞台にデビューしたベラスコの「同期」たち、ヒトラー、ルーズベルト、スターリン、チャーチル、フランコ、そしてフィルビーも既にこの世を去った。
ヒトラーはベラスコの助力で、生前の意思を今日まで伝えることに成功している。たとえば、現在のネオ・ナチの活発な活動がそれだ。いま世界に湧きだしている民族主義運動の基盤は、ベラスコが50年前にマルチン・ボルマン(ドイツ第三帝国最後の総統)らに手を貸して、根腐れさせなかった成果だそうだ。ロシアのジリノフスキー(自由民主党党首)やアラブ諸国の民族派指導者など、ネオ・ナチと同様の例は多い。それらの勢力がふたたび息を吹き返した現実を、ベラスコは没故の5人にかわって眺めている。
ルーズベルトが、ユダヤ系国際資本家との合作で誕生させたCIAの動きも、ベラスコの日々を飽きさせていない。レーニンが産み、スターリンが育てたKGB(ソ連国家保安委員会。ゲーべーウー=GPUの後身)の活動も同様である。ベラスコは、スパイのOBとして、CIAとKGBのどちらの「相談」にも乗っている。
◆
「エレクトロニクス(CDカード、つまりコンピューター)戦争」とベラスコが呼ぶ、国際金融戦争の最終的な宣言を「だれが」「いつ」「どこで」発動するかをベラスコは口にしはじめている。環境問題の重視をうたうその一方で、すでに開発済みのバイオ兵器やウイルス菌を活用している特定勢力の矛と盾の作戦の詳細も、書斎のファイルにとじ込んであるという。
ノーベル賞受賞者たちが隠しつづける素顔や、イギリス政府を指揮して中国市場を奪取しようとはかるイギリス系国際資本家の事業計画にベラスコは興味津々である。デモクラシー(民主主義)という言葉の裏に隠された「ユダヤクラシー」とベラスコが呼ぶ民主化が、中国全土をおおった場合の中国人の世界観を注意深く観察しているのである。隣国の韓国と日本にその前例があるから、中国の「ユダヤクラシー」化は時間の問題とか。
西暦2000年までは生きる、とベラスコは頑張っている。イスラエルが晴れて巨大な世界政治経済の司令塔を地中海に設置する日を確かめたいからだそうだ。その「司令塔の建設」計画はすでに始まっており、アラファト(PLO議長)も最後のご奉公に駆り立てられているのだという。
◆
日本人は、世界の動きが見えなくても生きのびる民族、とベラスコはいい放っている。地政学上の島国としての強みと、独自の宗教観(神道)があるから外敵の侵入を許しにくいのだそうだ。
だがその反面で、「国際化」と称して外国勢力の片棒を無原則にかつぐ日本人には要注意と警告する。
ユダヤ系スペイン人ベラスコの関心は、特定の国家にではなく、ユダヤの同胞に向けられている。だからこそ、あれもこれも「知っている」ということらしい。世間にはいわゆるユダヤ禍なる言葉もあるように、ユダヤ国際資本家の影響力は世界の端々にまで及んでいるという。非ユダヤ人を家畜や奴隷にする宗旨をもつ民族だ、と激しく非難する純粋なキリスト教徒もいる。ベラスコは、その通りだとも、そうではないともいう。
■Part-3
1984年の頃からベラスコは、回顧録の執筆を始めていた。過去に思いを馳せる黄昏の日々かと推察したのだが、それは大間違いだった。目の黒いうちは「現役」なのだそうだ。
1日24時間を情報収集活動に当てていた。健在のラモンとも連絡を絶やさず、地下のナチス情報網とも交信していた。のみならず、その他の「仲間ら」とも連携して「ユダヤ世界連邦政府」の動向を監視していたのである。こうした活動を続けるベラスコが「戦後」という言葉になんの意味づけをも与えないのは当然なのかもしれない。
西暦2000年の最初の10年までに我々のいう戦争は終結するだろう、その時点から「戦後」の文字を使うのが「良心的な歴史家」の責任だ、と不思議な戦争観を信条にしているのが、ベラスコだからである。しかしベラスコのご託宣を何人の人間が理解できるだろう。太平洋戦争が50年前に終わったと認識している我々にとって、ベラスコのいう二重底の戦争論にはハナから立ち往生させられてしまうほかはない。
ベラスコの話をもう少し聞いてみよう。
以下、ベラスコの発言である。
──────────────────────────────
ユダヤ民族がソロモン帝国樹立の具体化作業に入ったのは1838年。スイスのバーゼルで開催されたカハル(ユダヤ賢人会最高会議)の場で決定された。しかし事業の具体的日程は見送られた。
この会議でテオドール・ヘルツル博士らの支援で、アルゼンチンをイスラエル建国の地と決定した。国家樹立事業名称を「天井に舞うオーロラ」としたのだが、その後に帝国の本拠地が変更された。ヘブライ国家をアルゼンチンからイスラエルに変更したのだ。
その後さらに、国家名を「地中海帝国」と呼ぶことに決めた。この名称は1961年まで秘密にされたが、同年にニューヨークのホテル・ヒルトンで開催された賢人会で、「帝国」の呼称を「政府」に改称することが決まった。改称理由は、マスコミに「帝国」を非難喧伝されたためだった。そのあと「地中海連邦政府」の名称が世界に紹介された。
西暦2000年(21世紀初頭?)には、その名前が正式に世界に発表されるだろう。実験的なこの連邦政府の拠点は3ヶ所。エルサレム、トレド(スペイン)、バリローチェ(チリ)だ。
繰り返すが、ユダヤ民族は19世紀末に自前の国家が完成する確証をえていた。4000年の労苦を最後の場面でフイにしないために、完壁な独立つまり非ユダヤ人、反ユダヤからのどんな策略や干渉も徹底排除できる万全の体制を敷いた。
事実上の世界支配を果たしておけば、その構えは完壁だ。ユダヤ民族は、世界支配を第一次と第二次の大戦を手段に達成した。二度の大戦で、戦争当時国の富をユダヤ資本家に移動させて(非ユダヤ人の富を回収して)完全な世界支配を確実にした。
世間でいう「戦争」が、これだ。が、ユダヤ教が解釈する戦争は、国家樹立のための事業でしかない。あの戦争の当時国にとっては、第二次大戦の終結は戦いの終わりだろうが、その戦争を支配したユダヤ民族にとっては、目的達成過程の一瞬にすぎない。
したがって、ユダヤ世界連邦政府樹立の必要に応じた戦争は、いつ始まっても不思議ではない。いまや世界諸国は戦争を起こす自由も権限も失っている。戦争が一部の国際ユダヤ資本家と指導者らによってキャスティング・ボートを握られている以上は、そうなってしまうほかはないのだ。
■Part-4
ベラスコの口癖は、「和平は戦争の一時的中断にすぎない」である。どうやら、これがベラスコのいう「和平は戦争の一時的中断」の根拠なのだろう。日本人には馴染まない言葉だが、西欧化が進むなかでは、馴染まざるをえない言葉かもしれない。だが、馴染みすぎると、西欧式尺度がまかりとおって東洋的アイデンティティが失われる危険性もある。横文字は所詮縦文字ではない、と突っぱねるべきか。いや、そうもいかない。世界の中で、孤立化していては生きられない。やはり、和・洋のバランス感覚が要求される。
絶妙な平衡感覚を維持するには、民族・個人の中心に確たる軸が必要かもしれない。軸のことをいわば民族の原則と呼ぶべきかもしれない。
ベラスコは数年前に日本を訪れている。
帰国の際に、日本訪問の印象をたずねられて、「ドンデ・エスタ・エル・ハボン(日本はどこへ行った)」つまり「原則はどうしたのか」と一言残して成田から立ち去った。超スパイの目に映った日本は軸を失った危ない国なのだろうか。
── 当館作成の関連ファイル ──
|
第6章
|

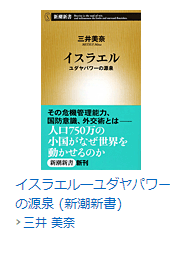

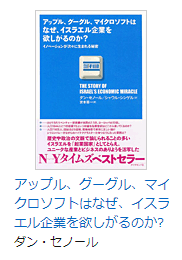
Copyright (C) THE HEXAGON. All Rights Reserved.